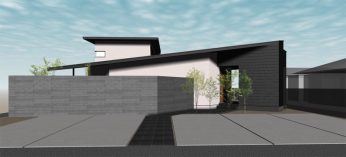レッドシダー ヨロイ張の壁
以前の現場blogで、内藤くんが現場視察で紹介した壁ですが、
近くで見るとこのように仕上がっています。↓

板と板を重ねながら張ることで立体感のある表情になります。
特に今回の拘りは、コーナー部分。
雑誌やウェブ上でも様々な納まり方があり、
木の断面が見えているものや、コーナー材をいれていたりする
ケースが見受けられます。
折角なのでスッキリと見えるようにしたい。
断面が見えないようにコーナーをまわしたい。
はじめは、どうやってやるの!できへんでしょ!
と叱責をかったものでした。
まぁいつもの調子でしたらそこで意気消沈するところですが、
何故だか今回はへんな意地が働いてしまいまして、
大工さんにお願いしモックアップを作成。
その出来栄えを確認しつつ仕上げることが出来ました。
大工さん泣かせのヨロイ張りの壁になりましたが、
良い感じに仕上がったのではないでしょうか。